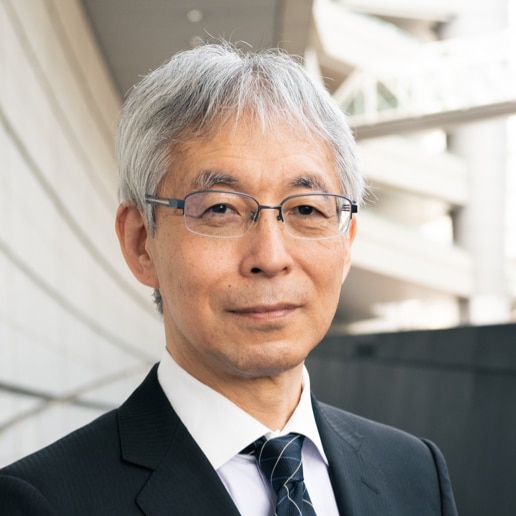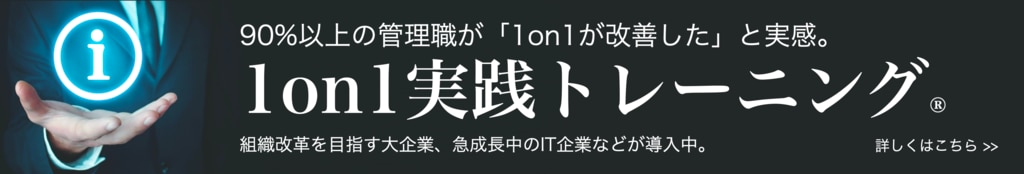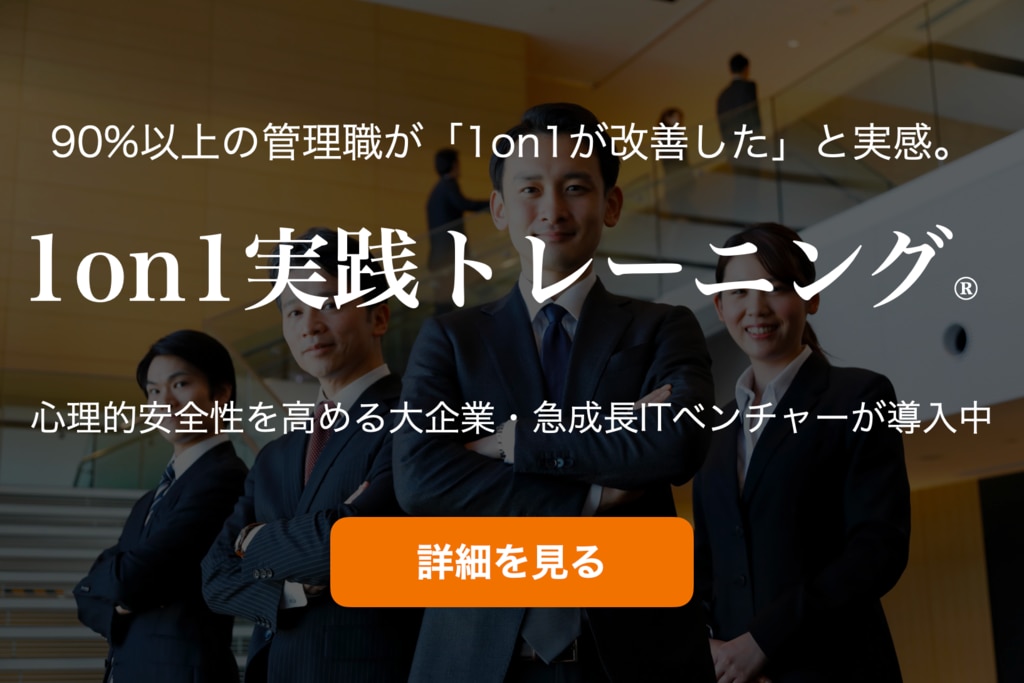災害時のリーダーシップ
先日発生した、東北地方を震源とする東日本を大きく揺さぶった震度6強の地震から2週間、いろんな事を考えさせられている。自分はリーダーとして適切に行動できただろうか。
東日本大震災の記憶と苦い経験がある。自問自答をしてみると、その経験や記憶から「こうすべきだった」という思いと、「結果オーライだからよかった」という思いとの葛藤かもしれない。
地震発生
2月13日 23時の地震発生直後、東京にいた私は直感的に「やばい」と感じた。数分後に会社の安否確認メールが発信され、その後メールとチャットで関係者が動き出した。早い。
1時間後には、被害の概況がわかり始め、大方の社員とその家族の安否も確認できた。誰もが自らの役割を認識し、特に現地のメンバーが迅速に動いてくれた結果である。
福島にある工場と配送センターは、いくらかの被害を受けたが幸運にも大事には至らなかった。
今回の現場対応は、10年前の震災の経験を十分に生かすことができたが、少しでも地震の状況が変わっていたら、大変な事になっていたのではないかと思うとゾッとした。
災害時に求められるもの
災害時と平時は何が違うのか。
まずは社員とその家族の安全の確保、これより大事なものはないと言い切れる。その上で業務を継続させることであるが、何を優先させるのか、何をやらないのかの判断も重要である。
弊社の場合は、患者の生死に関わる製品を扱っており、他社では代替がきかない製品を出荷することが最優先事項である。この点においても、平時の仕事の進め方とは全く異なってくる。
BCP(Business Continuity Plan - 事業継続計画)で決められた手順に従う。あとは時々刻々と変わる状況、限られた情報の中でどう迅速に判断し行動していくか。
チームをまとめ、安全を確保し業務を円滑に進めていくことが、リーダーに求められている。
リーダーシップ力を評価する
災害を含む非常時のリーダーシップのスタイルを見ると、実にそのリーダーの力量が見事に現れる。これは他者からの評価もあるが、自分自身の内省のチャンスでもある。
教科書通りにいかないのは言うまでもない。全体を把握する力、先を見通す力、行動力、発信力、決断力、コミュニケーション力、信頼、直感、覚悟などなど、総合力で乗り切るしかない。
こうした機会に、いつもと違う観点から自分のリーダーシップ力を評価してみてはどうだろうか。
今回の地震は、平時以上BCP未満と、微妙な対応が求められたが、同時に自らを振り返り、いろいろ考えるきっかけを与えてくれた。
「自分自身はどうあるべきであったか。」 今でも自分に問い続けている。