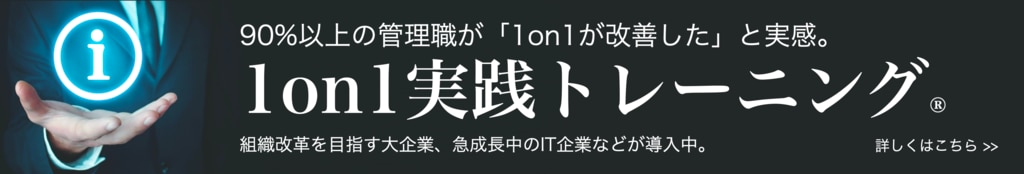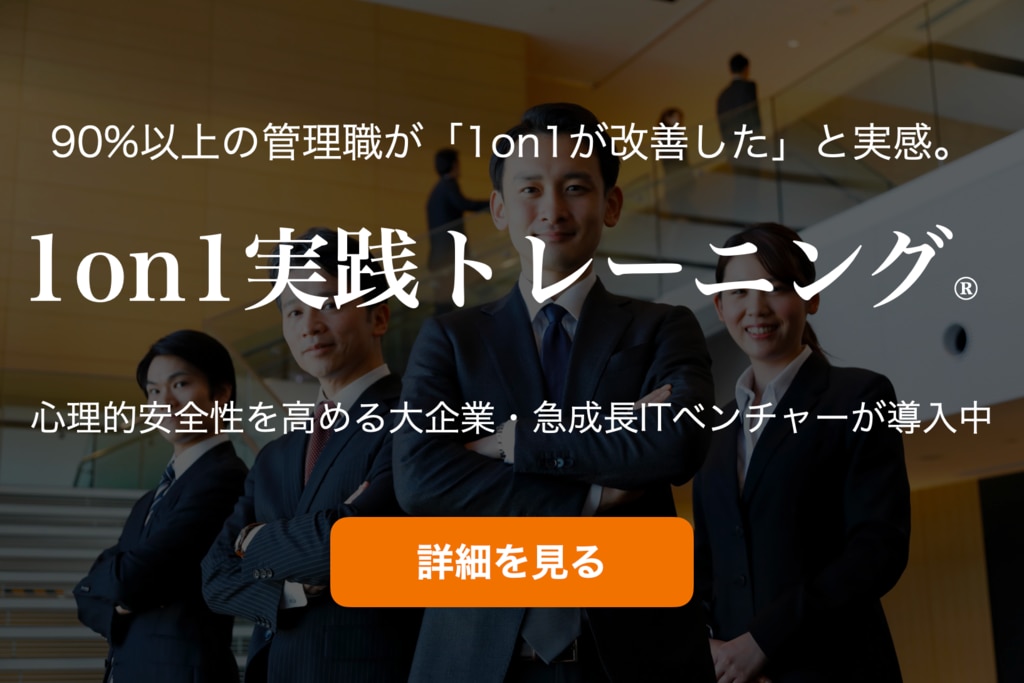事業を承継する、とは
最近、中小企業の経営者の方から、事業承継に関するご相談を受ける機会が増えています。
中小企業庁のガイドラインでは、経営者が事業承継の準備に取り掛かるのは、60歳に達する頃が望ましいと言われています。
しかし、実際には、引退を考える経営者が70歳前後とも言われ、そのほとんどが、後継者が不在か、十分に育っていないと言われています。
弁護士として、事業承継に失敗したり、対策不十分なまま経営者が亡くなり、紛争を招いた例を数多く見てきました。
そのため、早めの対策を考える経営者の方が増えるのは、とても良いことだと思います。
「事業承継」って、そもそも何?
もっとも、この「事業承継」という言葉、明確な定義があるわけではありません。
「後継者の確保」という観点で捉える方もいます。
事業承継税制が整備され、「相続税対策」という観点からも注目を集めています。
ただ漠然と、「自分の死後、会社はどうなるの?」という不安に襲われ、ご相談にいらっしゃる方もいます。
私が「事業承継」を考えるときは、承継する「事業」とは何か、という観点に立ち返ります。 経営者の方々が培ってきた「事業」を構成する要素、すなわち、
①人(経営)
②資産
③知的財産(目に見えにくい経営資源・強み)
という3つの要素を、信頼できる後継者ないし第三者に円滑に引き継ぐこと。 そのために、それぞれの要素をどうするか、皆さんと一緒に考えていきます。
「事業承継」で忘れてはならない、意外なこと
この「事業承継」を進めていくに当たって、私は大切にしているものがあります。
それは、経営者の方々の事業に対する「思い」です。
「事業承継」で、特に資産や知的財産の承継に注力し過ぎると、どうしても数字ばかりが先行しがちです。
いかに高値で会社を引き継ぎ、あるいは利益を上げるか、という視点だけが独り歩きして、事業を承継する本来の目的が失われてしまうこともあります。
その結果、事業は承継したものの、なんだか腑に落ちない、という経営者の方を、数多く見てきました。
だからこそ、私は、 “事業を承継した後、どんな未来を実現したいのか” という観点も、忘れてはならないと考えています。
これは、経営者だけでなく、時には後継者や従業員の方々にも参加してもらい、一緒に考え、掘り下げていくこともあります。
ここを忘れてしまっては、本当の意味で、事業を承継することはできないからです。
まとめ
このように、「事業承継」は、法務や税務などの専門知識に加え、コーチングのスキルなども活用しながら、経営者の「思い」を形にして、次世代にバトンを渡していく作業でもあります。
これは、一朝一夕で完了するものではなく、むしろ、ここからがスタート。
現在、第一線で活躍する経営者の方々には、ぜひ、少しでも早くこのスタートラインに立ってもらいたいと思います。
<PR>
飯塚 予始子 メンターのメンタリング・コーチングの体験セッション受付中! >> お申込み
月額9,500円からの継続メンタリングサポート >> Biz Mentor Plusの予定表について