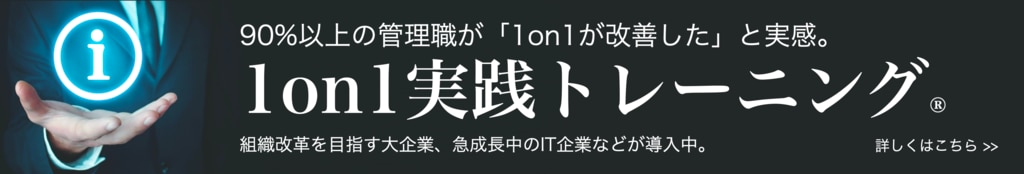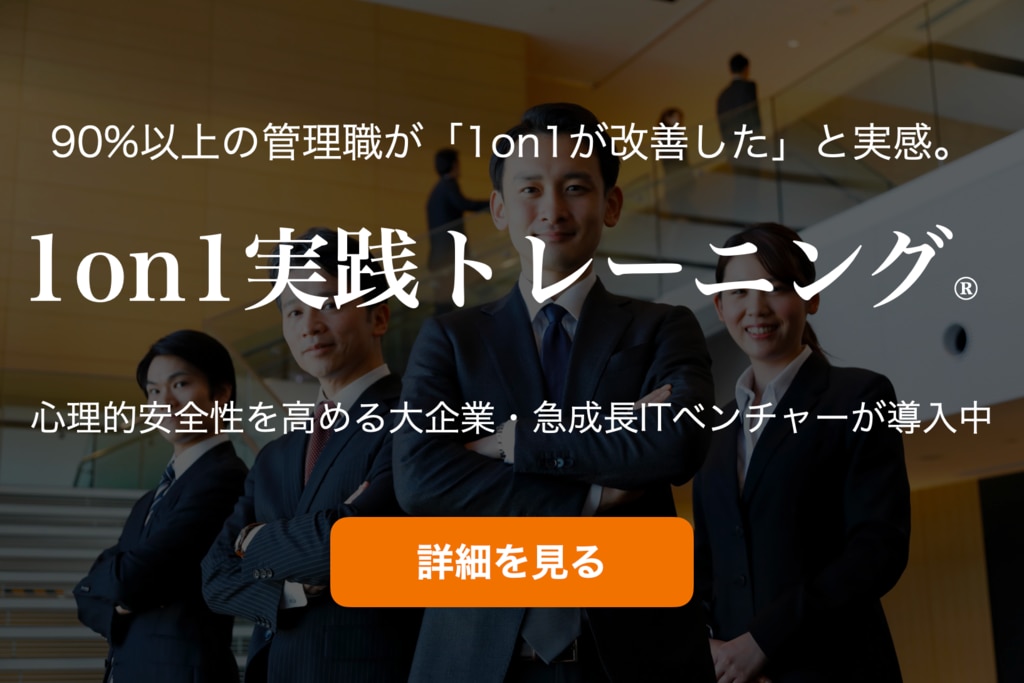「既成概念にとらわれない」リーダーになる
個性を受け入れ、一人ひとりが能力を発揮できる体制と環境を整え、個々を活かしていく組織づくりとしてダイバーシティ&インクルージョンの推進がされている企業が増えています。
そのとき、組織のリーダーには「既成概念にとらわれない」企業文化の醸成を求められることがあります。
「既成概念にとらわれない」とはどういうことか・・・リーダーとして、どのように取り組めばいいのでしょうか?
「既成概念」使い方と意味
既成概念は「既成概念にとらわれない」といった表現で、既成概念を批判的に捉える使い方が多くされています。
「常識にとらわれない」という意味で使われています。 「既成概念」と同じような意味で「固定観念」も使われますが、 「固定観念」とはそれが正しいと思い込んでしまい、変えることができない考えのことをいいます。
「観念」とは、人が物事に関して抱く主観的な考えや意識のことで、「概念」とは物事の共通性を取り出した意味内容のことをいい、両者は別の意味を持ちますが、私はここでは広く適用している客観的内容にも、固定された主観的な考えにもとらわれないという意味で、どちらも取りあげておきたいと思います。
また、既成概念」の類義語として「先入観」が挙げられます。「先入観」とは、初めに知った知識や情報にもとづいて作られた観念のことで、「既成概念にとらわれない」というとき、個人的な考え方を指す場合には「先入観にとらわれない」と言い換えることができると思います。
既成概念にとらわれないために
(1)先入観を捨てる
既成概念にとらわれて物事を見ると、本質を正しく評価できなくなります。思いこみで評価するので、新しいものを有効活用できなくなってしまうことがあります。
そのような時は先入観を捨て、公平な状態で物事を認識することが大切です。
仕事を長く続けていると、経験を重視して仕事を進めることが多くなり、過去の経験は貴重な情報であると同時に、先入観を生み出す危険もはらんでいることを認識しておきましょう。
知識や経験だけを基準にすると、今以上の仕事ができる可能性を逃すことになりかねません。
(2)常識で物事を計らない
自分の判断基準が、他人にとって普通とは限りません。常に自分だけの判断基準で物事を選択していると、既成概念が生まれてしまいます。
自分以外の判断基準を用いることで仕事に新たな価値を与えることもできます。
例えば、企業が価値あると判断しても、顧客にとって価値があるとは限りません。この場合は、顧客の持つ判断基準を利用して選択することが必要です。
(3)視点を変える
一方向からだけ物事を認識していると、いつの間にか固定観念にとらわれ既成概念が生まれてしまいます。
常に他の視点を意識して、物事を多面的な視点からとらえようとすることが大切です。
一つの仕事を長く続けている人ほど、自分の視点だけで仕事をしてしまいがち。時には別の側面から仕事をとらえると、今まで気付かなかった改善点や問題点が発見でき、柔軟で豊かな発想を生み出すことができるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
既成概念にとらわれるというのは、意識して生まれるものではなく、長く続けている内に凝り固まってしまうことがあります。
時には自分の仕事を振り返り、先入観で評価していないか、自分の常識にとらわれていないか、他者の視点を取り入れているかなど、メンター・コーチとともに自分自身を見つめ直してみませんか?