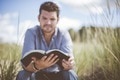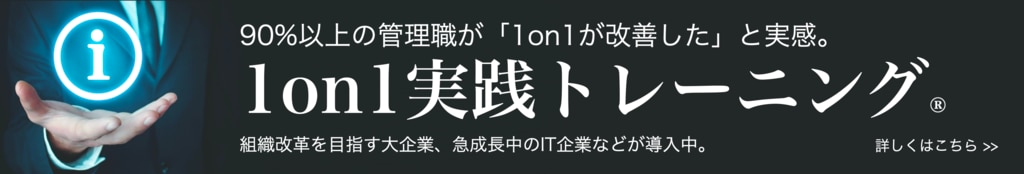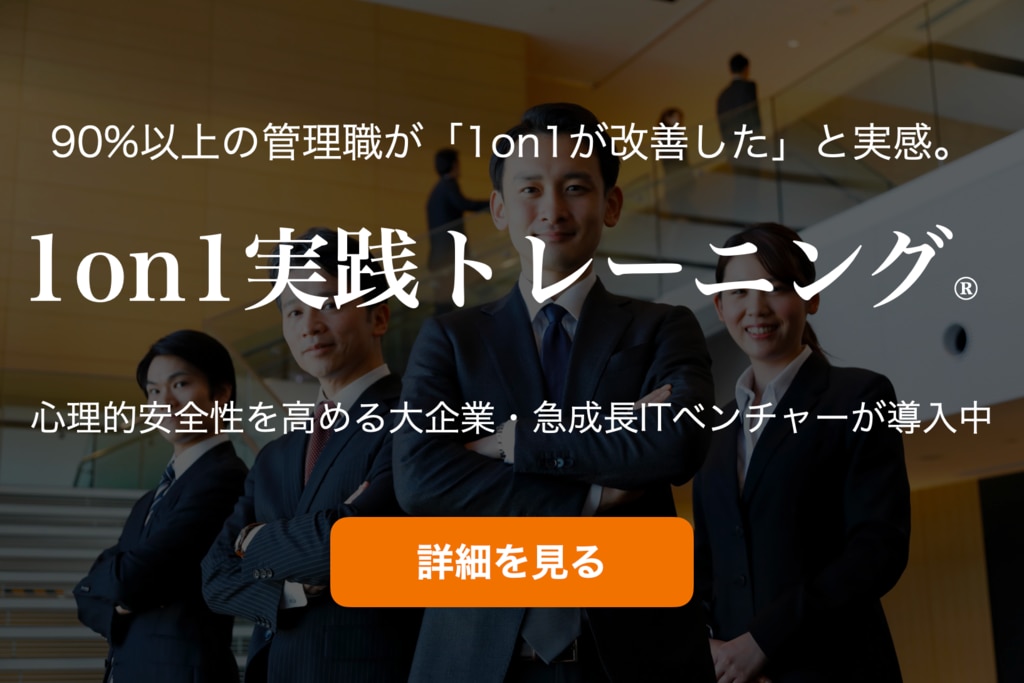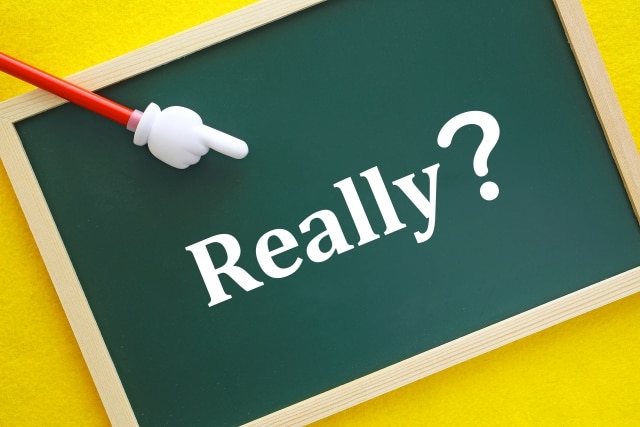
「正しさ」を疑う
先日、後輩指導に悩むKさんから相談を受けました。
Kさんが指導係を任されている後輩Oさんには、誰彼構わず正論を並べるクセがあります。
そのせいか、Oさんは、周囲と衝突したり、取引先と言い争いになることもあるそう。
Kさんは、その都度、相手が受け取りやすいように言い方を変えるなどの工夫が必要だと指導してきました。
しかし、正論なのに怒られる筋合いはないと、Oさんも腑に落ちない様子。
そんな「正論」を突き付けられて、Kさんも困ってしまいました。
「正論」=正しい?
正論とは「道理の正しい議論」。つまり、「正しい」ことが前提となっています。
「正しい」のであれば、周囲も取引先も納得してくれそうなものの、なぜかその「正しさ」が、怒らせる要因となるようです。
たとえば、KさんとOさんが所属するグループで、オンライン機器の利用方法に関し、導入されたばかりのルールがありました。
ところが、このルールを守っていたのは、Oさんただ1人。
結果、機器の利用にダブルブッキングが生じ、現場にちょっとした混乱が生じました。
その際、Oさんは、ルールを守っていた自分が「正しい」、その他が「間違い」として、守らなかった人たちを糾弾したのです。
たしかに、ルールはルールですから、Oさんは「正しい」はず。
でも、なぜか他のメンバーから総スカンを食らいます。
「正しい」はずが怒りを買ってしまった原因は、どこにあるのでしょうか?
「正しさ」は、時と場合で変化する
たしかに、ルールを守ったOさんは、「正しかった」のかもしれません。
しかし、上記の例で一番問題だったのは、導入されたばかりのルールが、現場で機能していなかったことです。
メンバーの中でも仕事量が少なく、時間の余裕があるOさんだからこそ守れたものの、それ以外のメンバーにとっては、手続が煩雑で、守る余裕もない内容でした。
つまり、Oさんの「正論」の基になっていたルールそのものが、現場にとって既に「正しい」ものではなくなっていたのです。
これは、現場の変化に応じて、「正しさ」もまた、常に変化していることを示しています。
そのため、Oさんの「正論」は、今の現場の中では微妙なズレとなって感じられ、そのことに納得できない他のメンバーを怒らせることになったのです。
このことに気づいたKさんは、Oさんに、いつも自分が「正しい」とは限らないことや、「正しい」「間違い」のいずれかで片づけられる問題ばかりではないことを説くようになったといいます。
自分は「正論」をぶつけないと断言できるか?
とはいえ、あなたも、相手に「正論」をぶつけてしまっていることはありませんか?
それは必ずしも、仕事場で、とは限りません。
むしろ、家族やパートナー、友人など、自分と近い距離にある相手に対しては、この「正論」をぶつけがちです。
その背景には、「あなたなら分かって当然」という期待や、思い込みが存在するケースも多くあります。
でも、あなたにとって「正しい」ことが、相手にとっても「正しい」とは限りません。
自分の「正しさ」を疑う視線を、常に意識したいものですね。