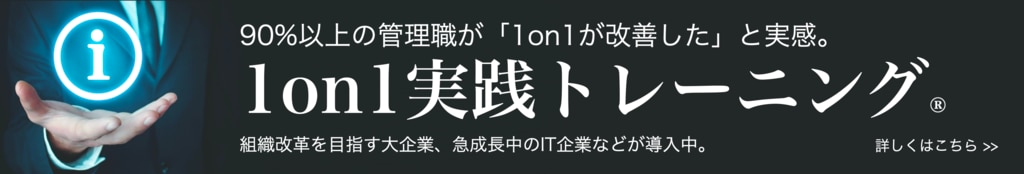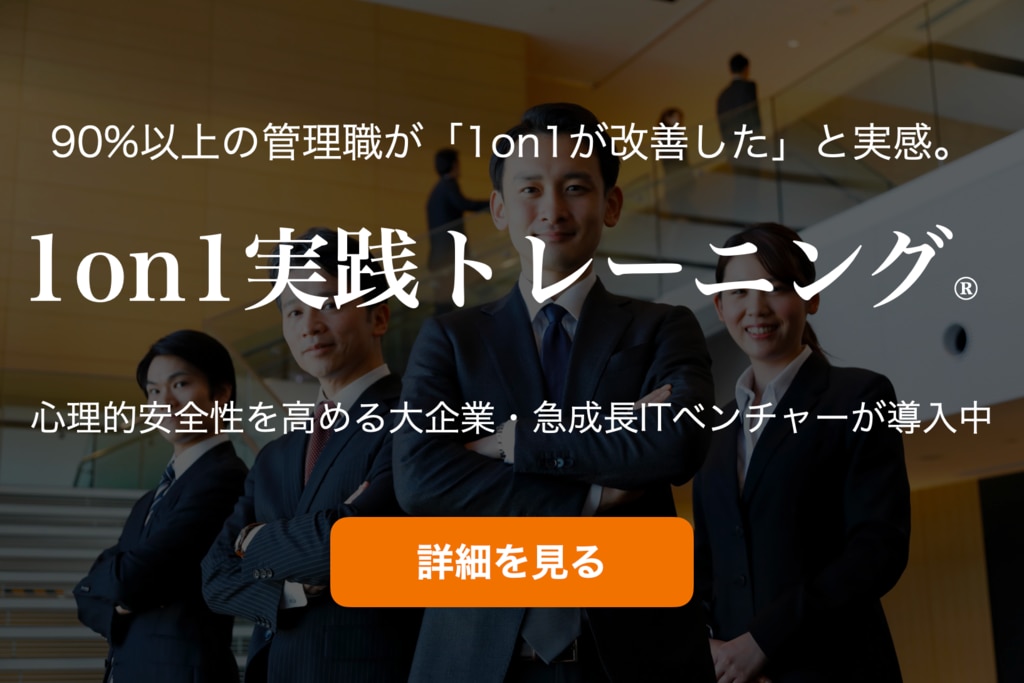発想力の養い方
先日「管理職の方が身に付けたいスキル」というアンケート調査結果を見ていたところ、「コミュニケーション力」「課題解決力」に並んで「発想力」というスキルが上位に並んでいました。
今までBiz Mentorブログのテーマとして「発想力」というワードを思い浮かべることはなかったのですが、自分自身発想力を養う為に取組んでいることがあることを思い出し、本日はこのテーマで記載させて頂きます。
発想力を養う場面
私はコーチングコーチの他、企業研修講師の仕事もしています。
「管理職向け」「営業職向け」など階層別にカリキュラムを組んでいますが、その時大切にしていることに「クライアントの声を反映すること」「コンセプトが明確であること」などがあります。
「新たな研修プログラム作成時」や「新たなコンセプトを考える」とき煮詰まってしまうときがあり、このような時に発想力が必要になります。
このような場面で発想力を発揮できるよう私が取組んでいることが3つありまして、今回はその手法を紹介させて頂きます。
①読書
私が発想力を養うために行っていることの一つに「読書」があります。
その実施方法は「知りたいことをテーマにした本を読むこと」です。
先日このようなことがございました。
私はマーケティングについて勉強できる本を探しに書店に行きました。
そこで手に取ったのが森岡毅氏著「USJを劇的に変えたたった一つの考え方」という本です。
この本はとても面白く引き込まれるように読んでいったのですが、245ページに書かれていることに目を奪われました。
行動を変えるために必要な手順について解説されているのですが、それは「価値観を共有する」「意志を固める」「スキルを身に付ける」「行動を変える」という手順です。
この手順を見て私は閃きました。『この手順は私が伝えていきたいことの解説に引用できる』と。
それからは講義に使うテキストに「森岡さんの書籍の245ページからの引用」ときっちり書いた上で私の思いを伝えることに役だたせて頂いています。
このような気づきも発想力を養う上で役立っていると思います。
②有識者の方と意見交換をする
私が発想力を養うために行っている他の方法に「有識者の方と意見交換する」ということがあります。
特に煮詰まったときに行っています。
私は「専門分野」としてもっているものはさほなく、多くのことを自力で発想することは困難なためです。
先日もこのようなことがありました。
「日本の労働賃金が30年変わっていない」「アメリカは平均年収は200万円以上上がっている」「イーロンマスクが買収したツイッター社の社員に週80時間以上の労働を課している」ことなどから日本の働き方改革の是非について考えていた時のことです。
世界を対象に活躍されている有識者の方の友人に伺ったところ、とても為になるご意見を頂きました。
そして私は気づきを得て自分の信念を貫いて「ワークライフバランス」を良くするための講義を続けていくことを決めました。
このことも頂いたご意見から発想を飛ばすことで着地できたことで「有識者の方と意見交換をする」ことも発想力を養うトレーニングになると改めて思いました。
③セルフコーチングを行う
私が発想力を養うために行っていることとして最後にご紹介する手法は「セルフコーチングを行う」ことです。
私は昨年8月の起業以来多くの課題に直面し、発想力を発揮できたからこそ乗り越えれたことが幾つもあります。
「本当に起業して大丈夫か」に始まりまして「今回ご提案頂いたことはお受けした方が良いか」「この方との協働はそろそろ終えたいが本当にそれでよいのか」など決断すべきことがたくさんありました。
そんな時に活用したのが「セルフコーチング」の手法です。
手順にそっていくつも場面設定をし、それぞれの結末がどうなるか発想を飛ばして考えました。
そしてその中で最善と思われることを選択し実行に移してきました。
今振り返ってみて大方その判断は正解だったと思っています。
このようなことから「発想力を養う」うえで有効な手段として「セルフコーチング」をご紹介しています。
なお「セルフコーチング」につきましては一般社団法人日本リレーショナルリーダーシップ協会代表理事の林英利氏著「一瞬で自分を変えるセルフコーチング」という書籍で詳しく紹介されています。
ご興味のある方はご一読されることをお勧めします。
まとめ
今回のブログは「発想力の養い方」をテーマに書かせて頂きました。
最後に改めてご紹介した手法をまとめさせて頂きます。
- 「読書」は発想力を養う上で有効な手段である
- 「有識者と意見交換をする」ことは発想力を養う上で有効な手段である
- 「セルフコーチングを行う」ことは発想力を養う上で有効な手段である
以上です。
これらの手法が読者の皆さんの参考として頂ければ本当に嬉しいです。
これからもブログの記載を続けて参りますので宜しくお願いします。