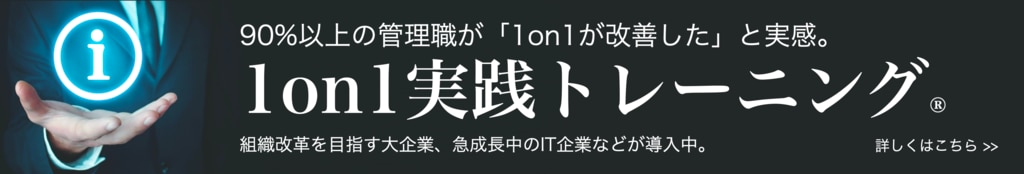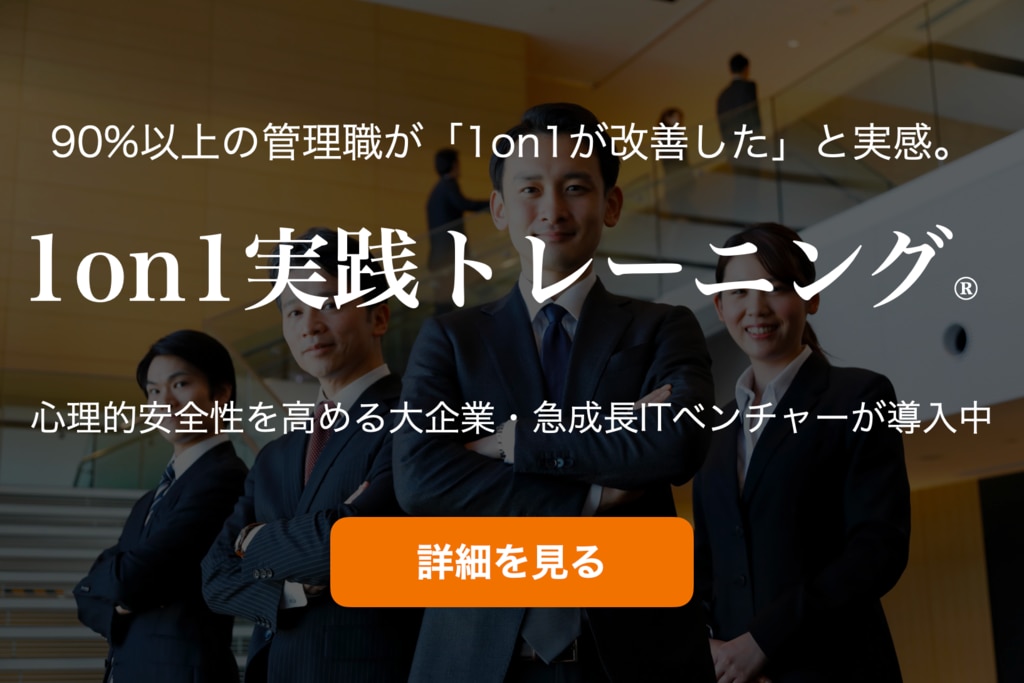知っていることと出来ること
概して言えば中小企業経営者は勉強家、読書家が多いと感じます。
会社を良くするための情報を常にどん欲に求めて様々な勉強会に参加したり、本を読んだりしています。
一方、勉強熱心さが会社の業績に必ずしもつながらないケースも見受けられます。
その理由は知っていることと出来ることの壁だと考えています。
学びのワクワク感
経営に関する本やセミナー、勉強会は世の中にあふれています。
経営者の在り方、経営理念の浸透、自走型組織のつくり方、 効果的な人事評価制度、社員の育成の仕組みなど、多種多様な学びの機会が存在しています。
日々、様々な課題に直面する経営者は、その課題に対する答えを見つけようと懸命に学んでいきます。私自身も正にそうでした。
学んでいる間は非常に充実した気持ちになり、実行計画を立てているとワクワクした気分が沸き上がってきます。
目の前の問題に対処するための学びをしている間は、高揚感に包まれやる気が高まっていくのです。
実践への壁
しかし学んでいる時にはやる気になっているのに、少し時間をおいていざ実践する段階になると途端に気分は重くなっていきます。
実践していく中で待ち受ける様々な困難を想定すると、「まだ早いじゃないかな」とか、「もっとも良いやり方があるのではないか」などとやらない理由を考え始めます。
そして結局、何もせずに また新しい次の学びのインプットに勤しみ始めてしまうのです。
これを繰り返していると、学びマニア、計画中毒のような状態になります。
インプットから計画立案までは熱意をもって進めるが 実践することは少ない、そして経営に関する事であれば、あれも知っている、これも知っているという頭でっかちになっていきます。
こうなると実践への壁は更に高くなります。
すでに学んで知っていることなので、どこかでまた誰からヒントを得たり、アドバイスを受けたとしても、「あーそれならもう知っている」と思ってしまい、実行する意欲がでないのです。
ダイエットとリバウンドを繰り返していくと痩せにくくなるのと同じように、学びと計画立案を繰り返していると、ますます実践できなくなっていきます。
知っていること=知識ばかりが増えていき、出来ること=実践は増えていかない、「やるべきことはすべてわかっているのですが。。。。」と言って一向に実践しない、経営者としてかなりまずい状況に私も何度も陥りました。
なぜ実践できないのか?
では、この知っている事と出来ることの壁が生じる原因はどこにあるのでしょうか?
その原因は、様々だと思います。
私自身の経験では、まず失敗を恐れる気持ちがありました。
実行しなければいつまでも計画は完璧であり、大切な経営資源を失うこともなく自分も傷つかずに済みます。失敗を恐れているといつまでも実践できません。完璧主義も一因です。
「もっと良いやり方があるはず」とベストを求め続け、結局何もやらないことになりました。
更には怠け心も大きな要因でした。
経営における大体のことは、実践する段階が一番大変でエネルギーを使います。
机上で学び、計画をしている段階は楽しくても 実践に伴い様々な課題を乗り越える必要があり、いつの間にかその苦労を回避する癖がついてしまうのです。
失敗を恐れ、完璧なやり方を求め続けるうちに、いつの間にか実践する苦労を回避するようになってしまうというパターンに 私は陥ってしまいました。
経営の本質は実践にある
経営者は学者でも評論家でもないので、経営の本質はやり実践にあると思います。
知っていることを出来ることにするために必要なことは何でしょうか。
まずは「鉄は熱いうちに打て」の例えの通り、関心を持って学んだことを計画に終わらせず、時期尚早であっても学んだことをすぐに行うことです。
十分に準備ができてからなんて言っていても、経営者はいつも忙しく新たな課題を抱えてしまい十分な準備なんていつまでもできないのです。
学んだことは即実践するという心構えを持ち、実践というアウトプットが出来なければ、新しい学び、インプットはしないといった覚悟が大切です。
また最大の問題は経営者には基本的に管理する上司がいないので、実践から逃げることができてしまうのです。
色々な言い訳をして、やりたくないこと、大変なことを後回しにしたり、やらないことにすることが可能なのです。
それを防止するために、私は年度の経営指針書にやるべき課題をあげて、指針発表会で皆に宣言するようにしています。
全社員が参加する経営指針発表会で宣言してしまえば、経営者の一存でなかったことにはできないので、学びを実践に繋げられます。
まとめ
経営者にとってより良い経営者になり、良い会社を創るために学ぶことは大切です。
しかし学びを実践に結び付けられなければ、むしろ学びはマイナスにもなります。
知っていることを出来ることに繋げて経営の実践を積み重ねていくために、自分に甘くならないように経営の伴走者としてコーチを活用することも効果的です。