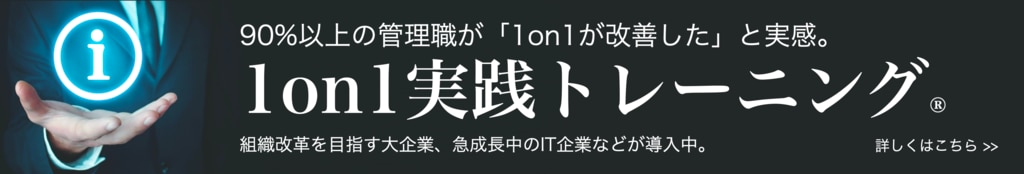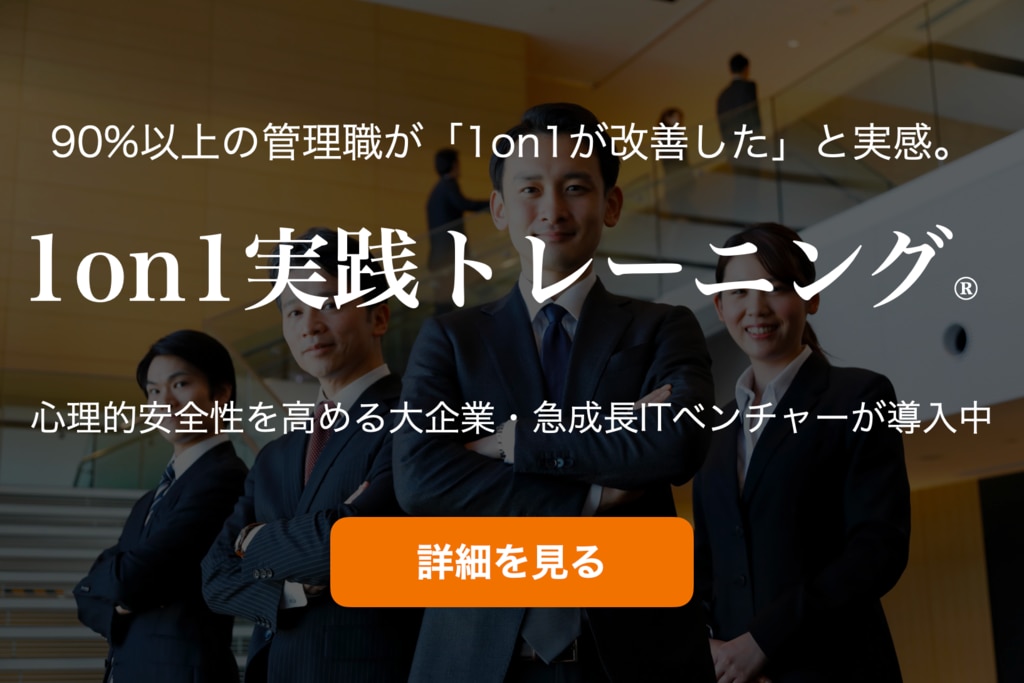人生100年時代に備える「リスキリング」の勧め
「リスキリング」という言葉をよく耳にするようになりました。政府も5年間で1兆円を投じるとのこと。
では実際にどのように対応したら良いのでしょうか?
今回は私の経験も少し振り返りながら考えて行きます。
私自身の経験
転職後2ヶ月で社長から退職勧奨を受け途方にくれた状態で、藁をもすがる気持ちで初めて受けたコーチングセッション。
その衝撃的なクライアント体験をきっかけに、その後私は自らもコーチングスクールで学び、さらに母校での講師も経験。
そして近々はコーチングの品質を向上させる目的で国際コーチング連盟(ICF)の認定資格も得ました。
現在は日本でコーチング文化を更に広めていくために、ICF認定アセッサー資格を取得すべく勉強中です。
好きが高じてここまで来た道のりで「天職」を得たという感触と同時に、「挑戦」を継続する中で少しずつですが、能力開発がなされたのだと改めて感じます。
リスキリングのための「前提条件」
P・F・ドラッカーは著書(*)の中で「自らの成長に責任を持つ」と記していますが、社会の急速な変化に対応するため、学び直し(リスキリング)の重要性が高まっています。
若い時に身に付けたスキルだけで、人生100年時代に適応するのは難しく、自らが「当事者意識」を持って、リスキリングに取り組むことが急務と言えます。
そのために先ずは、リスキリングの自分なりの目的を明確にしたいです。
私は個人的には「自分をup-to-dateに保つこと」としていますが、皆さんはどのように言語化しますか?
自分がup-to-date、つまり現代的・最新式であるかどうかを見極めるためには、自ずと情報収集が必要となります。
世の中の動きにアンテナを立て、トレンドに敏感であることが求められます。
リスキリングのための「心構え」
・継続的に学ぶ
「英語をどれくらい使いこなせますか?」などと、英語を短期的に習得するプログラムを売り込む広告を目にすることがあります。
翻って考えてみて、皆さんは母国語である「日本語」をどれくらいの期間学び、練習し、使って今のレベルまで到達したでしょうか?
学びとは時間がかかるものなのです。従って学びは「継続する」ことが鍵を握ると考えられます。
そして継続的に学ぶにはモチベーションを維持するための工夫を要します。
そこでやる気を維持する「自分なりの」方法を編み出したいです。
定期的に検定試験を受けて自分の進捗度・成長度を可視化し、計測するのも一法でしょう。
また短期的には、自分へプレゼントやご褒美を与える、というのも良い方法だと思います。
・強みを活かす
一方、そもそもリスキリングにおいて、どのようなスキルや技能に取り組んだら良いのでしょうか?
世の中のトレンドを勘案して、と上述しましたが出発点は自分の「強みを活かす」視点です。
仕事を通じて培った強みや得意技を一段階発展させて、今後の仕事にどう活かせるのか、活かしたいのかを検討したいです。
もちろん趣味や、仕事を離れた特技・好きなことを掛け合わせるのも良い方法だと考えます。
「将棋好き」が高じて将棋を教えることを実際に仕事にしている人が私の近くには存在します。
ここで重要なのは「チャレンジ精神」です。
自分が従事していて楽しいことであれば、挑戦することは厭わないと想像されます。
リスキリングのための「具体的行動」
・目標及び計画を立てる(短期的と長期的)
羅針盤なしの航海は回り道をしたり、途中で座礁したりで、目的地にはなかなか到達できないでしょう。
しかし余りに長い航海では先が見えずに不安にもなります。
そこで3~5年程度の長期的な視点はもちろんですが、短期的な目標と計画も立てると効果的だと考えられます。
これはモチベーション維持にも役立つでしょうし、社会の変化や市場トレンドに合わせていち早く対応できる、軌道修正できるメリットもあります。
6ヶ月スパンの短期目標を用意したいです。
・アウトプットや実践を重視した学習方法を採用する
学習のための学習、は継続が難しいことは多くの皆さんが既に体験されていることだと思います。
私は学生時代、運動部に長年属していましたが、「練習のため」の練習ほど辛いものはなく、「試合に勝つため」の練習に多くの時間を割きたいと強く感じていました。
リスキリングも同様に、学んだことを業務で使ってみる、習ったことを知り合いに説明する・教える、などアウトプットの場を創ることは非常に効果的です。
・共に学ぶ「仲間」を持つ
皆さんもこれまで、一度は「通信教育」を受講したことがあると思います。
これほどまで続けることが難しい学習方法は無い、と私は感じています。
そこで同じ志や目標を持つ「仲間」と一緒に、リスキリングを進めることを強くお勧めしたいです。
習ったことをお互いに共有する、職場でどのように活用・実践するかを一緒に検討する、分からないことをお互いに教え合う・補い合う。
私が56歳で大学院へ入学した時、将にこれを実践しました。
若い仲間からIT分野の新しい知見を教えてもらい、一方、私の実務経験を仲間と共有する。
世代を超えたナレッジ・トランスファー(KT)が自然に実現した場だったと今でも実感できます。
まとめ
今回は「リスキリング」に焦点を当て、具体的にどのように進めて行ったら良いかについて記しました。
これまで培ってきた経験やスキルを出発点としつつも、時代の流れやトレンドにあった人財に「しなやかに」進化していくことで、100年人生を豊かに過ごしたいと思います。
ドラッカーは同著書の最終章で、我々にこのように問うています。
「あなたは何によって憶えられたいか」
*参考文献:「プロフェッショナルの条件」P・F・ドラッカー