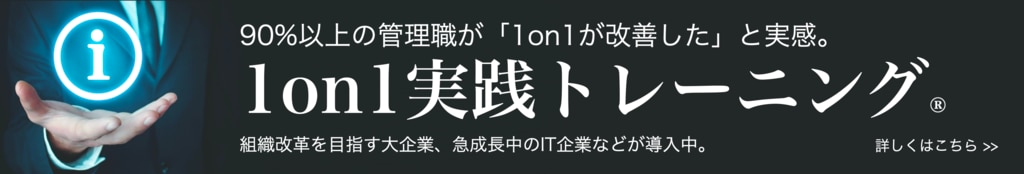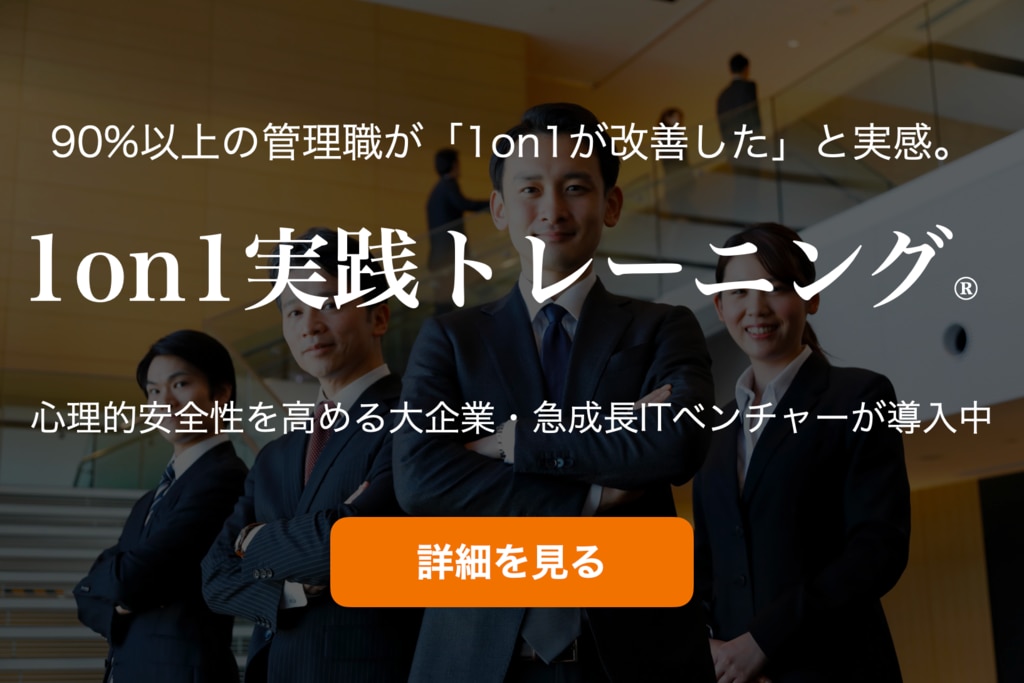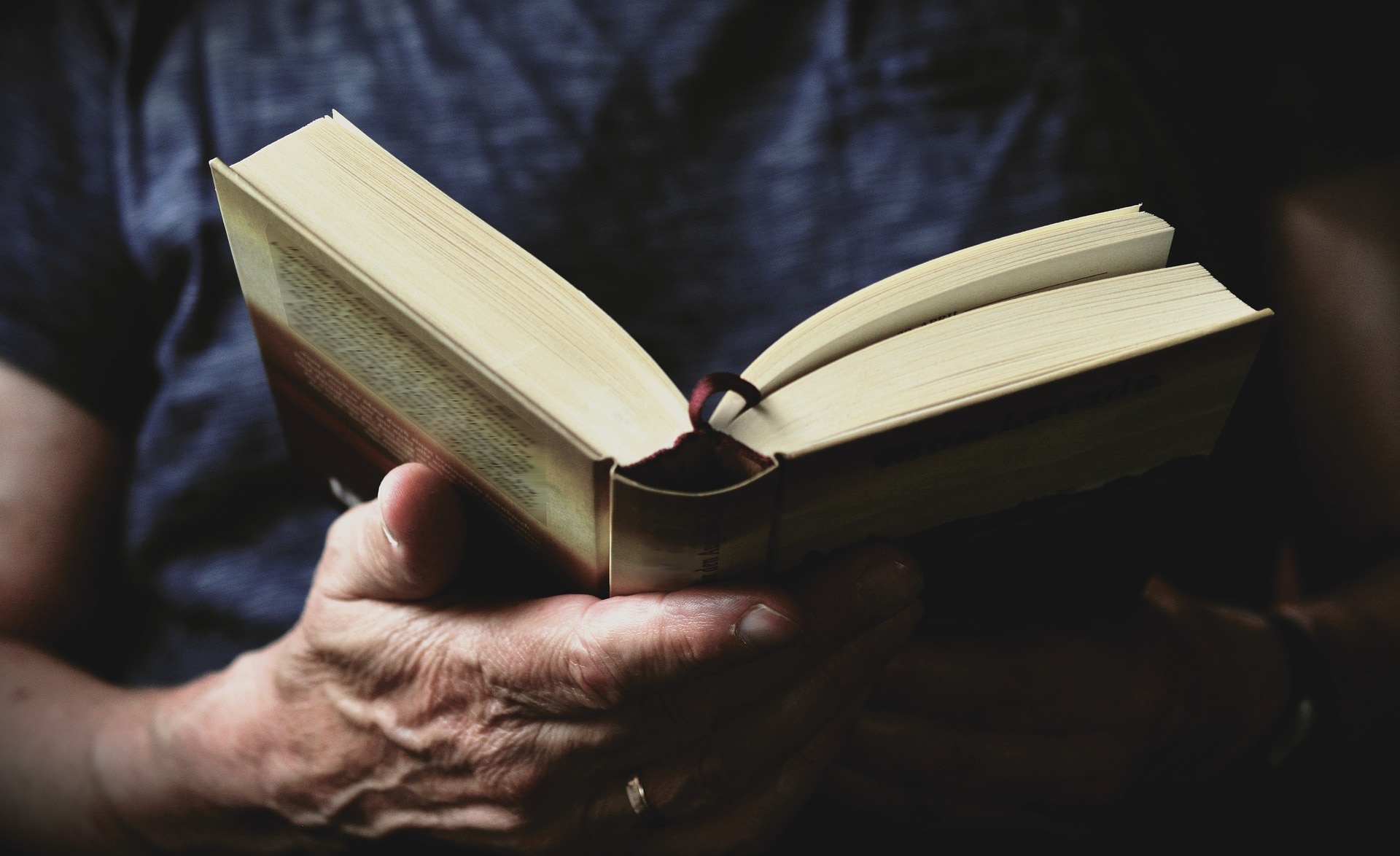
読書のすすめ:リーダーにはビジネス書ではなく「小説」を!
ビジネスパーソンは普段の自己啓発が大切です。
特に読書は手軽な方法であり、リーダー職の皆さんはビジネス書を手に取ることが多いものと思います。
そこで敢えて今回は視点を変えて、管理職・リーダーにとって「小説を読むことの効用」というテーマでお伝えします。
私のエピソード:娘との読書会
「お父さん、この『海辺のカフカ』という本、読んだの?」
ある夏の日、大学生の末娘が本棚にある文庫本を手に取って突然話しかけてきた。
「村上春樹だよね?その昔に読んだ。有名な作品だけど内容はすっかり忘れてしまったな!」
こんな会話から始まった娘との読書会。
同じ小説をそれぞれで読んで行き、時おり感想を共有するというもの。
そしてしばらく読み進めて行くと「お父さん、上巻を読み終えたけど…..この後はどうなっていくの?」
そう娘に問われても、ストーリーを忘れてしまっている私は答えられない。
そこで閃いた。「この後の展開なんて忘れたよ!だから下巻を読み始める前に、自分でこの後のストーリーを想像してみるのはどうだろう?創り出すという意味での創造でもいいよ!」と。
管理職・リーダーが小説を読む効用
同じ読書でも、ビジネス書とは色々な意味で異なる小説を読むことは、ビジネスパーソンにとってどういう効用がありそうでしょうか?いくつか挙げてみます。
【洞察力・感性・共感力を磨く】
小説の中で登場人物たちは、それぞれに異なる価値観や経験を持っているように描かれています。
その登場人物と同じ視点を持ち、どの様に行動するかを読み取ることで、人間の本質や心理について深く理解することができます。
このような洞察力は、ビジネス上で重要な意思決定を行う際に、より正確な判断を下すために必要不可欠な要素です。
また、小説を読むことで共感力を養うこともできます。
小説には登場人物たちが抱える悩みや問題、それに対する解決策が描かれています。
このようなストーリーを通じて、ビジネスパーソンは自身のチームメンバーや顧客といった他者の立場や考え方を理解し、彼らと共感することができるようになるでしょう。
そして共感力はチームメンバーのモチベーション向上や顧客ニーズの把握につながるため、リーダーにとっては重要な能力と言えます。
【異なる視点を持つことで創造力を養う】
小説には様々な性格の人物が登場し、それらの人々が織りなす人生ドラマを味わう一面があります。
読者は主人公になりきって読み進め、考え方や価値観の異なる人物に出会いながらストーリーが展開します。
「何故こういう行動を取ったのか?」主人公に没入しつつも、一方、色々な登場人物の言動を俯瞰しながら読み進めることは、職場の人間関係やメンバーの得意・不得意を考慮しながら業務を進める職場を、小説という別の形で疑似体験することになります。
このような体験が、異なる視点を気付かせてくれたり、「自分ならこういう道筋で意思決定をする」などの創造的思考のトレーニングにもなると期待できます。
【コミュニケーション力・表現力を養う】
さらに小説を読むことで表現力や語彙力など、状況に適応したコミュニケーション力を養うことにもつながります。
小説の中で描かれる登場人物たちが、物語の進行に応じてコミュニケーションをとり、意見を交換していく様子は、ビジネスにおいて必要なコミュニケーションスキルを学ぶための良い教材となります。
特にビジネスの現場では、リーダーはチームメンバーと効果的にコミュニケーションを取ることはリーダーにおいて不可欠な能力と言えます。
まとめ
私も最近ではビジネス書を読む頻度は増えましたが、これまでの読書歴を振り返ってみると、かなり多くの小説を読んできたように感じます。
大学時代には渡辺淳一の小説にハマり込み全集まで読破して、本気で医師になろうかと思ったほどです。
またその昔、数多くの作品を読了した井上靖や福永武彦は、30年以上経った今、読み直したりしています。
当時見えなかった人間模様や、気付かなかった視点を改めて教えられるように感じます。
【さて、娘との読書会はどうなったでしょうか?】
「えー、下巻ではそういう展開になるの?そんなストーリーは考え付かないわね!やっぱり村上春樹ならでは、なのね!」娘は続きを読み進めながら感嘆の声を上げていた。
娘との読書会はその後もしばらく、読んだ本の感想を共有する形で続いている。
たまには皆さんも、小説を読むことの効用、そして醍醐味を味わってみませんか?
*参考文献:「ビジネスパーソンが小説を読むべき理由」クリスティーン・サイファート投稿(Harvard Business Review)、2020年4月8日