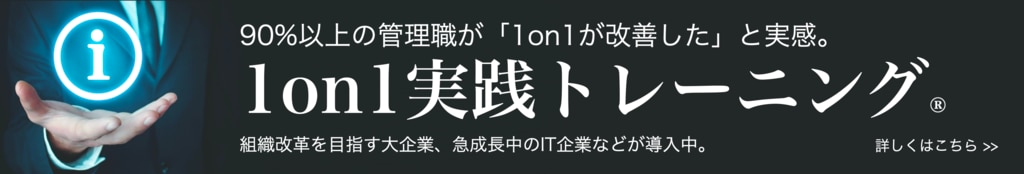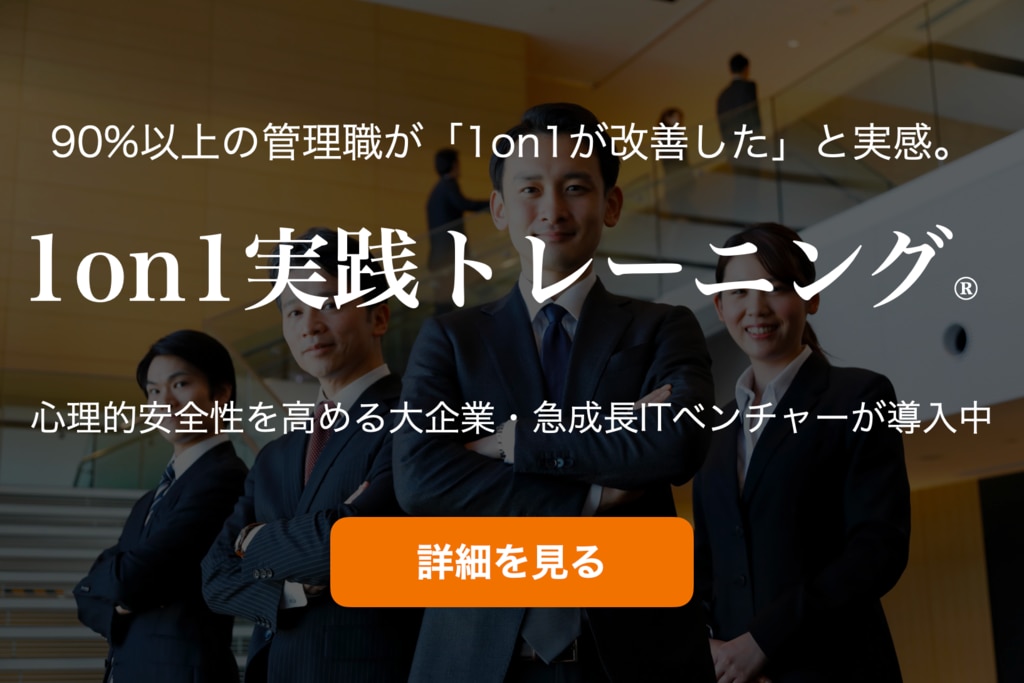プレイング・マネジャーとは「贅沢」なジョブである!
「うちの会社の管理職って、ほとんどがプレイング・マネジャーなんですよ!」
付き合いのある会社社長が、半ば諦め気味にぼやくのを耳にしました。
これ以外にも私は、プレイング・マネジャーが揶揄されたり、問題視される場面に何度も出くわしています。
しかし本当にそうなのでしょうか?
今回はプレイング・マネジャーのサバイバル法を探ります。
エピソード:30年前、私が新任係長になった時
「砂村、毎晩お前は遅くまで一人で残業しているけど、何にそんなに忙しそうにしているんだ?」
振り返ると夜の会議からデスクに戻った課長が話しかけてきた。周りを見回せば職場に残っているのは自分だけだ。
少しむっとして私は「例のプロジェクトの議事録を書いているんですよ!」
「そうか。議事録は読ませてもらっているが、毎回お前が自分で書いているのか?」
その時私は、その3ヶ月前に課長から投げられた問いかけ、―お前はいつまで一人で仕事をするつもりなのか?―をふと思い出していた。
プレイング・マネジャーの問題点
「課長はなぜ、そんな問いかけを私にしたのだろうか?」
当時を振り返りつつ、プレイング・マネジャーの問題点を挙げてみます。
1.メンバーや部下の仕事を奪う
現場を熟知していることから、メンバーや部下の代わりにマネジャー自身が業務をこなしてしまうということが起きます。
これは取りも直さず部下たちの業務の習熟化や成長の機会を奪ってしまうことになります。
そして長期的な観点では人材育成が進まず、係や課全体のスキルアップを阻んでしまうでしょう。
2.マネジャー自身の能力開発を阻害する
能力開発の点はマネジャー自身にも当てはまります。
メンバーや部下など自分以外の人を通じて結果を出す、成果を上げることが管理職の仕事です。
忙しさにかまけて、もしくは多量な業務をこなすことに焦点が当り、マネジャーとしての役割認識が低いと管理職能力を磨く機会を失わせてしまうリスクがあります。
3.マネジャー自身が超多忙になる
私のエピソードにもある通り、現場仕事を対応しながら管理職としての仕事もこなす、プレイング・マネジャーはどうしても業務過多になりがちです。
業務量による物理的な負荷に加えて、組織上位層からの期待とプレッシャーもあってメンタル面も心配です。
プレイング・マネジャーという「贅沢」なジョブ
問題点だけを列挙して改めて感じるのは、プレイング・マネジャーの仕事を難しくしているのはその名の通り「一人二役」だからです。
即ち組織やチームの管理職でありながら、実務や現場で自らも積極的に活動や業務をこなすスタッフ的な一面も有するのです。
そこで視点を変えて、一人二役なので大変とか難しい、リスクがあると一方的にネガティブに捉えるのでなく、能力開発やキャリア形成の観点で捉え直すと「贅沢な」ジョブと言えるのではないでしょうか?
プレイング・マネジャーならでは利点も考慮しつつ、生き残りの方向を探ってみましょう。
プレイング・マネジャーの「サバイバル法」
一人二役という贅沢なプレイング・マネジャーという機会を最大限活かすためには、以下の視点が必要と考えられます。
1.現場仕事と管理業務のバランスを意識する
現場仕事に精通していて、実務的なノウハウを部下に共有・伝授できることがプレイング・マネジャーの最大の利点で、現場で発生する課題をいち早く解決できるメリットがあるのです。
しかし業務が出来るからこそ、つい現場仕事をやってはしまいがちです。
これでは一人二役の贅沢さを活かしきれているとは言えません。
そこで自分なりの線引きを意識したいです。
そしてその際「現場仕事」対「管理業務」の時間配分の切り口に加えて、業務内容や分野の視点で境界線を検討するのも効果的だと考えます。
例えばマネジャー自身が得意な分野は完全に部下に任せつつ、新しい分野の業務は部下と協業するなど意図を持ってメリハリを付ける、というのはどうでしょうか?
2.制約下で最大の成果を出す工夫をする
時間的及び人的リソースが限られた中、どのように最大の成果を上げるのか?この課題に取り組む良い機会と考えたいです。
部下からの共感や相互の信頼関係を構築しやすいプレイング・マネジャーではありますが、管理職が業務を代行し処理スピードを上げるだけでは、真の意味での業務の効率化は図られているとは言えないです。
自分の後継者と目する人材には思い切って権限移譲を進め、異なる視点や視座から業務内容を根本的に見直す、オープンな発想を醸成するもの一法です。
また一方、指導が必要なメンバーや部下には丁寧にOJTを進めることで、部署全体の業務効率を上げるように工夫することも心がけたいです。
3.キャリア構築の方向性を検討する
一人二役を今後も続けるのか、世の中の動きに追随しながら現場業務を更に極めて、より高度な業務専門職を目指すのか。それとも管理能力を更に高めて究極の管理専門職を目指すのか?
一人二役をこなしながら、自分自身のキャリアの方向性を検討するのにはプレイング・マネジャー職は非常に良い機会と考えられます。
昨今「ジョブ型雇用」への移行が頻繁に話題になっています。
欧米では基本的にジョブ型雇用と言われており、一方日本企業も経済のグローバル化に伴い従来の「メンバーシップ型雇用」からの脱却、と言葉だけが一部先行している感もあります。
日本企業で今後、どの程度「ジョブ型雇用」が進むのかは予想が付かないものの、業務の「専門化」はなお一層進捗すると予測されます。
顧客や市場ニーズが高度化し、変化が早いVUCAの時代においては、ある特化された分野で一定レベル以上の専門性は絶対必要と考えられるからです。
まとめ
とかく揶揄されがちな「プレイング・マネジャー」ではありますが、現場スタッフと管理職の両方を上手くバランスさせることで、早期キャリアアップを実現可能とする「贅沢」なポジションとも考えられます。
賢く「一人二役」をこなしてみませんか?
*参考文献:「7000人のプレイングマネジャーを変えた8つの法則」生田洋介、2012年7月2日、中経出版