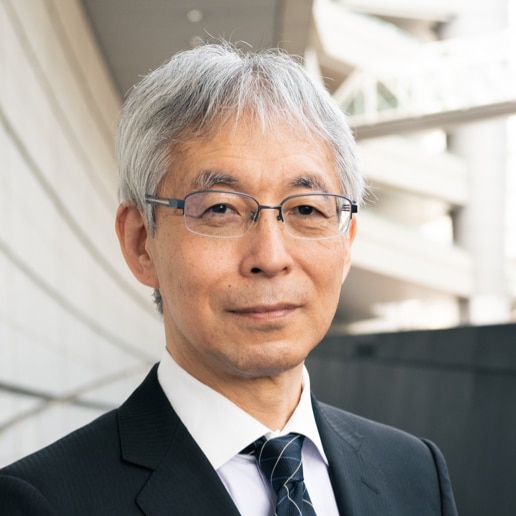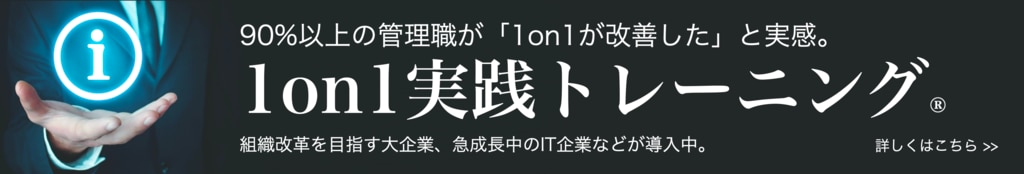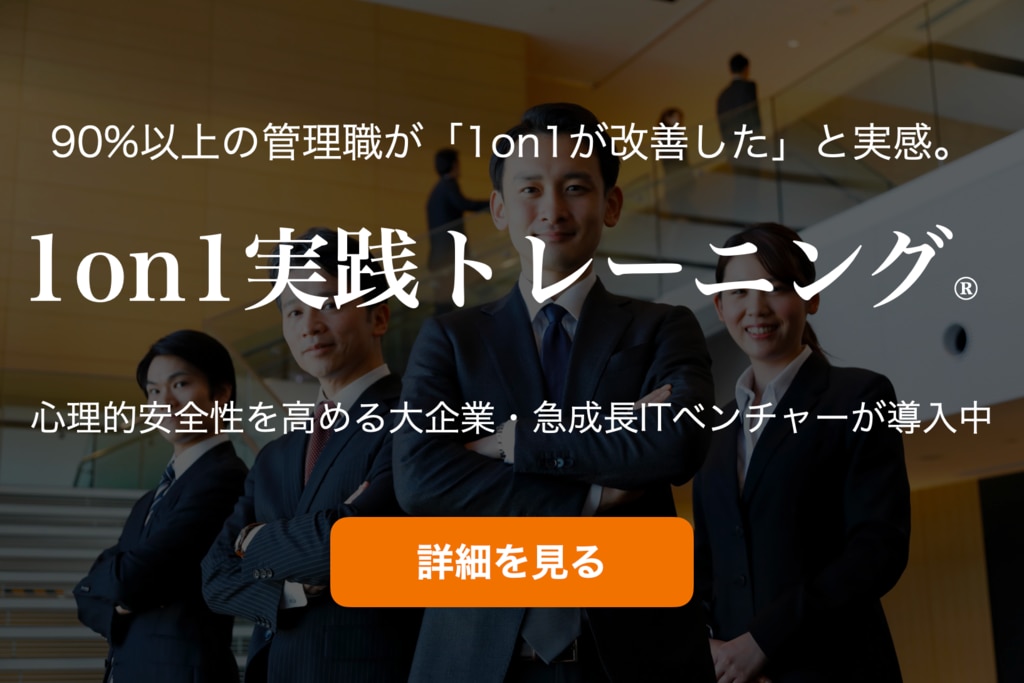心理的安全性が保たれた職場とは
コロナ禍で在宅勤務が増え、リアルな人との交流が制限されている中で、より心理的安全性の確保が大事であると感じている。
私たち中間管理職にとって、自分の心理的安全性が保たれている状態に身を置けているか、自らがその状態を作り出せているかが、自分及びチームのパフォーマンスに大きく影響を及ぼしている。
心理的安全性とは何か?
心理的安全性とは、サイコロジカルセーフティー(Psychological Safety)と言って、ハーバード大学の教授が概念を提唱し、Googleがこの考え方をビジネスに活用させた。
正式な定義があるようだが、ビジネスのシーンで言えば、職場がオープンであり、チームのメンバーがお互いを尊重しあい、忖度なく自由に意見の交換ができ、不安を感じること無く仕事ができる状態のこと。
この状態が十分確保されていると、心理的安全性が高く、チームの生産性が向上するとされている。
ここで全てを説明することはできないので、興味のある人は是非、Webや書籍などで調べてみることをお勧めする。
私の職場では
私自身、グローバル組織に所属し、多くのステークホルダー(利害関係者)と仕事をしているが、私を含む上位の組織においては、心理的安全性が保たれていると感じている。
もしかしたら、私には少々の事ではへこたれない耐性があるのかもしれないが、思い通りにいくかどうかは別として、お互いを尊重し、言いたいことを言える環境が整っていると思う。
逆に、130名程いる自分の組織は、末端まで心理的安全性が保たれているかは不安なところがある。
特に、組織的に私から距離のあるところにいる人は、何かしらの不安を感じているかもしれない。
心理的安全性を保つには
心理的安全性を保つには、それを阻害する不安を排除する必要がある。
- 無知だと思われることへの不安 – 知らないと言えない
- 無能だと思われることへの不安 – 失敗を隠したい、過ちを認められない
- 邪魔していると思われることへの不安 – これを言ったらみんなに迷惑
- ネガティブだと思われることへの不安 – 否定的な発言は控える
これらの不安を取り除くことによって、職場は明るくなり、自由闊達な、生産性の高い集団に変わっていく。
リーダーとして、自分は何を言われても受け入れる準備ができているか、失敗したときに責任を取る覚悟はあるかなど、自問してみるのも良いだろう。
全部できなくても、できるところからやってみることが大切だと思う。
まとめ
特にコロナ禍においては、コミュニケーションの手段がオンラインとなり、ちょっとした雑談の機会も減っている。
在宅勤務で、一日だれとも話さない、そのような部下がいるかもしれない。
もしかしたら、自分は良くても、チームは思っている以上に心理的安全性が保たれていないかもしれない。
このような時代であるからこそ、安心して働ける職場をつくるために、心理的安全性を点検してみてはいかがだろうか。