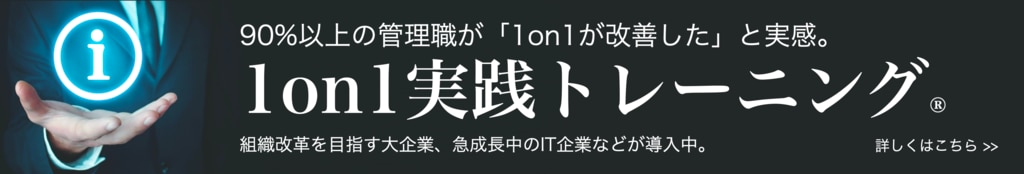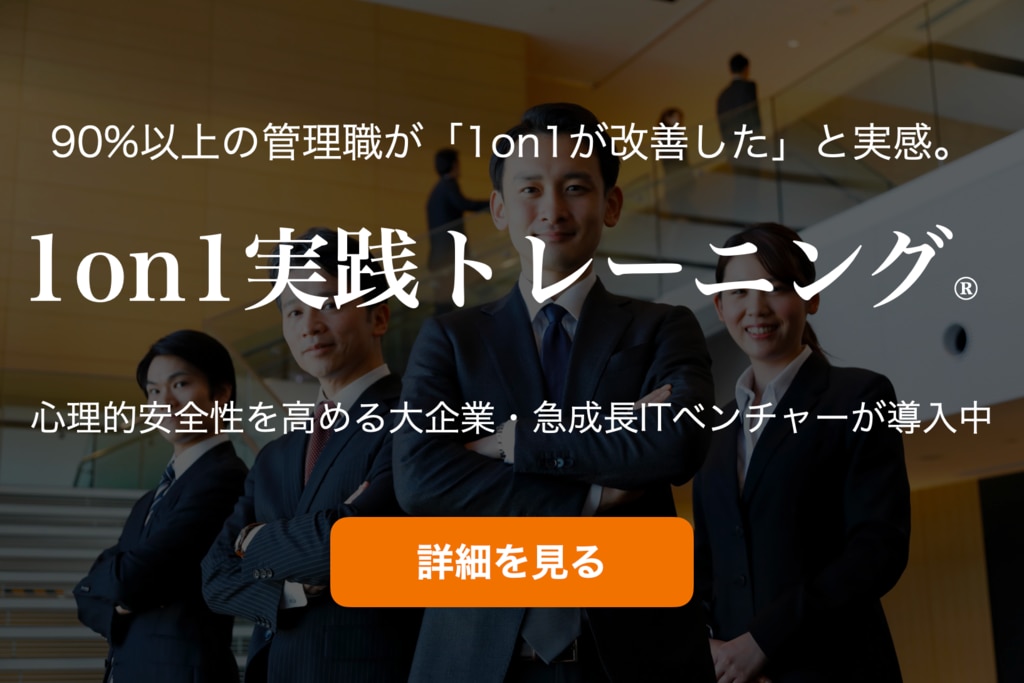職場で「コーチングが使えない」と嘆くリーダー達へ
あなたが使うコーチングは、「思ったより活かせない」とか「いつもの会話になってしまった」という状態に陥っていませんか?
心当たりのある方は、ぜひこちらをご覧ください。
職場でコーチングは機能しないのか?
私は自社の一事業として、コーチングスクールの地方拠点を運営しています。
毎月のようにコーチングの講座を開講しているのですが、そこに参加される約9割の方がビジネスパーソン、さらに、そのうちの約6割の方がリーダーという要職に就かれています。
この状態が意味するものは、ビジネスの現場やリーダーの方にとって、コーチングスキルは有効である、あるいは、有効になりそうだという認識があるからだと私は考えています。
ところが、コーチングを学習した方々が、職場でいざコーチングを実践してみると、「思ったより活かせない」とか「いつもの会話になってしまった」というような感想や意見を伺います。
果たして、これは、一体何が原因なのでしょうか?
今日のブログでは、プロコーチとしての立場から、考えられる要因を幾つかご紹介したいと思います。
職場でコーチングが機能しない3つの原因
① 部下にコーチングを理解してもらっているか
コーチングはそもそもコーチ(上司)とクライアント(部下)が協働関係のもとに行われるものです。
協働(≒対等)である以上は、双方がコーチングに対する同じ認識を持ち合わせている必要があります。
具体的には、コーチングとはどういう性質のコミュニケーションなのか、ティーチングやカウンセリングとどう異なるのかということを、上司がまず認識し、部下にきちんと説明しておく必要があります。
② 部下との間に合意形成が図れているか
上記①に関連しますが、ここで言う合意とは、具体的には、「取り交わすべき同意事項」と「守るべきルール」のことであり、合意形成とはこれを定めておくということです。
例えば、前者の例では、コーチング時に話すテーマや目標、時間・場所などを決めておく、後者の例では、「(上司は)秘密を漏らさない」とか「(部下は)正直に話す」といったことを守るということです。
③ 部下との間に信頼関係が築けているか
上記①・②と同じぐらい重要なこととして、両者の間に信頼関係が築けていることが挙げられます。
そもそも信頼関係が築けていなければ、部下は上司に本音を話そうとは思わないものです。
そのために、上司は、部下との日頃からの関わりもさることながら、その場で何でも話せる雰囲気をつくる工夫をすること(例えば、アイスブレイクを行う等)が大切になってきます。
まとめ
職場でコーチングが機能しない原因として、上記に挙げた事柄がすべてとは言えませんが、私の経験上、いずれかが影響している可能性は大きいと考えます。
もし、あなたが、職場で「コーチングが使えない」と感じているようでしたら、一度、検証してみることをお勧めします。
大石 典史 メンターのコーチング・メンタリング体験セッション受付中! >> こちら
月額9,500円の継続メンタリング・コーチングサポート >> Biz Mentor Plus+