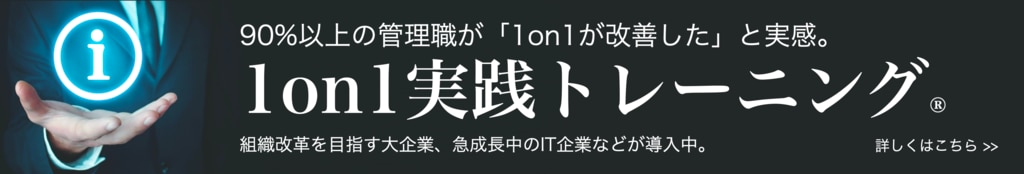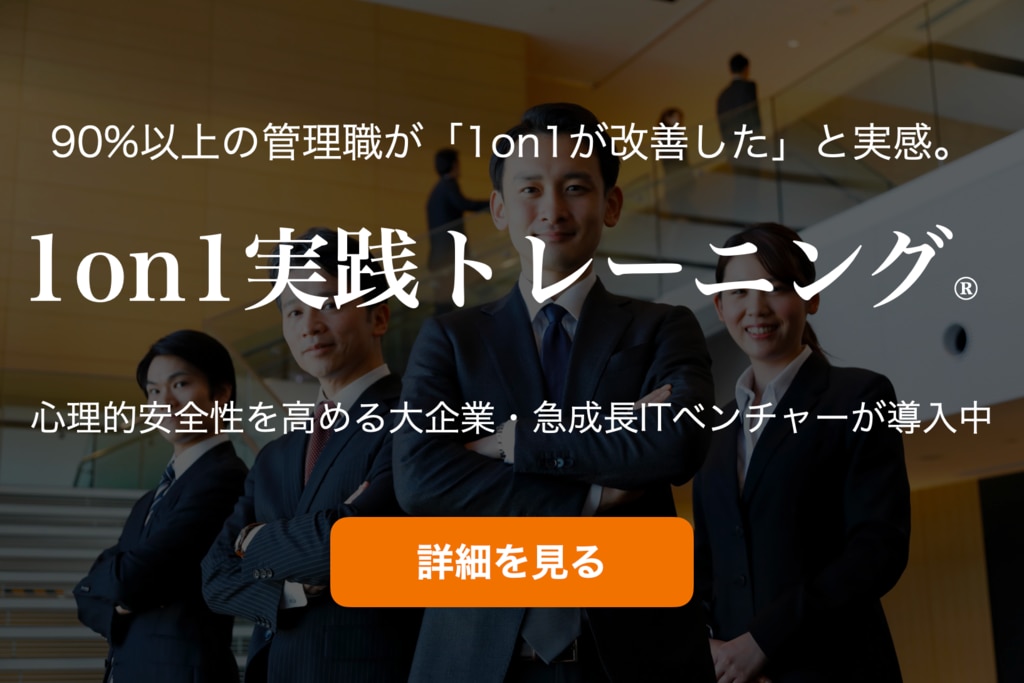千利休の教え − その9 − シンプルだけど
これまで紹介してきた利休百首は、茶道の精神や点前作法の心得などを、初心者にも分かりやすく憶えやすいように歌にまとめたものです。
点前作法については、「道具は畳の目に沿って置け」、「特定の茶入れは横から持て」、「柄杓で湯を汲む時は九分目まで」と、結構細かな事を言っています。
流石に、そのような事ばかり言われ続くと、場合によっては嫌気がさしてきたりします。
しかし、後半の98番目に次のような歌があります。
「茶の湯とはただ湯を沸かし茶を点てて飲むばかりなる事と知るべし」
シンプル、単純明快です。 「茶の湯は、湯を沸かして、茶を点てて飲むだけの事」なのです。
うん、これなら私でも出来る。さっそく今日からでも千利休の教えを実践出来る気になりますね。
100番中98番目の意味
でも冷静になると、この歌は98番目(後ろから3番目)にある事に気づきます。
そうか、97番目までしっかりと稽古してきたから、身に付けてきたからこその歌なんだと。
シンプルな歌の背景にある、精神と作法の両面の積み重ねの大切さを感じ取れます。
品質は一定に保たれていますか
湯を沸かしてお茶を点てるだけの事ですが、今日も明日も同じレベルで出来るでしょうか。
実際、お茶を点てる時は、気温や湿度をはじめ、道具の取り合わせや、お菓子との相性、もちろんお客様の状態に合わせた心配りが大事な要素になってきます。
日々の仕事も常に同じ条件であることは少ないでしょうが、それでも一定レベルの品質を保つには、やはり日々の積み重ねが大事になります。
積み重ねの大切さを実践すると同時に、メンバーに対しての助言でも役立てください。